マンダラチャート(Mandala Chart)は、日本の経営コンサルタントである松村寧雄氏が開発した目標達成やアイデア発想のためのツールです。このツールは、中心に主要なテーマや目標を配置し、その周囲に関連するサブテーマやタスクを配置することで、全体像を視覚的に整理し、具体的な行動計画を立てるのに役立ちます。
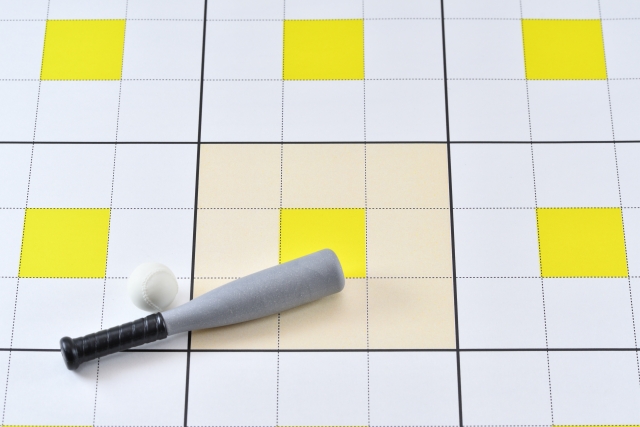
マンダラチャートの構造
マンダラチャートは、以下のような3×3のマトリックス(9マス)を基本単位としています:
- 中央のマス: 主要なテーマや目標を記入します。
- 周囲の8つのマス: 中央のテーマに関連するサブテーマや具体的なタスクを記入します。
この基本の9マスを拡張して、各サブテーマもさらに詳細に展開することができ、全体を多次元的に視覚化することができます。
使用方法
- 目標設定: まず、中央のマスに主要な目標やテーマを記入します。
- サブテーマの洗い出し: 中央の目標に関連する主要なサブテーマやタスクを、周囲の8つのマスに記入します。
- 詳細化: 必要に応じて、各サブテーマも中心に置いて、再度マンダラチャートを作成し、さらに詳細な行動計画や関連事項を洗い出します。
- 優先順位の設定: 各タスクの重要度や優先順位を考慮して、実行計画を立てます。
利点
- 視覚化: 複雑な問題や目標を視覚的に整理することで、全体像を把握しやすくします。
- 創造性の促進: サブテーマやタスクを細分化することで、新しいアイデアを発見しやすくなります。
- 実行可能性の向上: 具体的な行動計画を立てやすくし、目標達成に向けたステップを明確にします。
マンダラチャートとロジックツリー
共通点
- 視覚的な整理:
- マンダラチャート: 中心の目標やテーマを中心に配置し、その周囲に関連するサブテーマやタスクを配置することで、全体像を視覚的に整理します。
- ロジックツリー: 中心に主要な問題や目標を配置し、そこから分岐して関連する要因やサブテーマを階層的に展開していくことで、問題の構造や解決策を視覚化します。
- 階層的な構造:
- マンダラチャート: 中央の目標からサブテーマへと展開し、さらに各サブテーマを詳細に展開することで、階層的に目標やタスクを整理します。
- ロジックツリー: 中央の問題や目標から枝分かれしていく形で、階層的に問題の要因や解決策を展開します。
- 問題解決と目標達成の支援:
- マンダラチャート: 目標達成に必要な要素を具体的に整理し、行動計画を立てるために使用します。
- ロジックツリー: 問題の要因を分解し、解決策を明確にするために使用します。
- 細分化による明確化:
- マンダラチャート: 主要なテーマを細分化して関連するサブテーマやタスクを明確にします。
- ロジックツリー: 大きな問題や目標を細分化して具体的な要因や解決策を明確にします。
- 全体像の把握:
- マンダラチャート: 中心の目標とその周囲のサブテーマを一目で把握できるようにすることで、全体像を見失わないようにします。
- ロジックツリー: 階層的な構造により、全体の問題や目標とその要因や解決策の関係を一目で把握できるようにします。
違い
- 構造とフォーマット:
- マンダラチャート: 3×3のマトリックスを基本単位とし、中心から放射状に展開する形式。
- ロジックツリー: ツリー状に分岐して展開する形式。
- 用途の焦点:
- マンダラチャート: 目標設定と達成のための計画立案に重きを置いている。
- ロジックツリー: 問題の原因分析や解決策の検討に重きを置いている。
これらのツールは、問題解決や目標達成のための強力なサポートを提供し、状況に応じて使い分けることで効果的に活用できます。
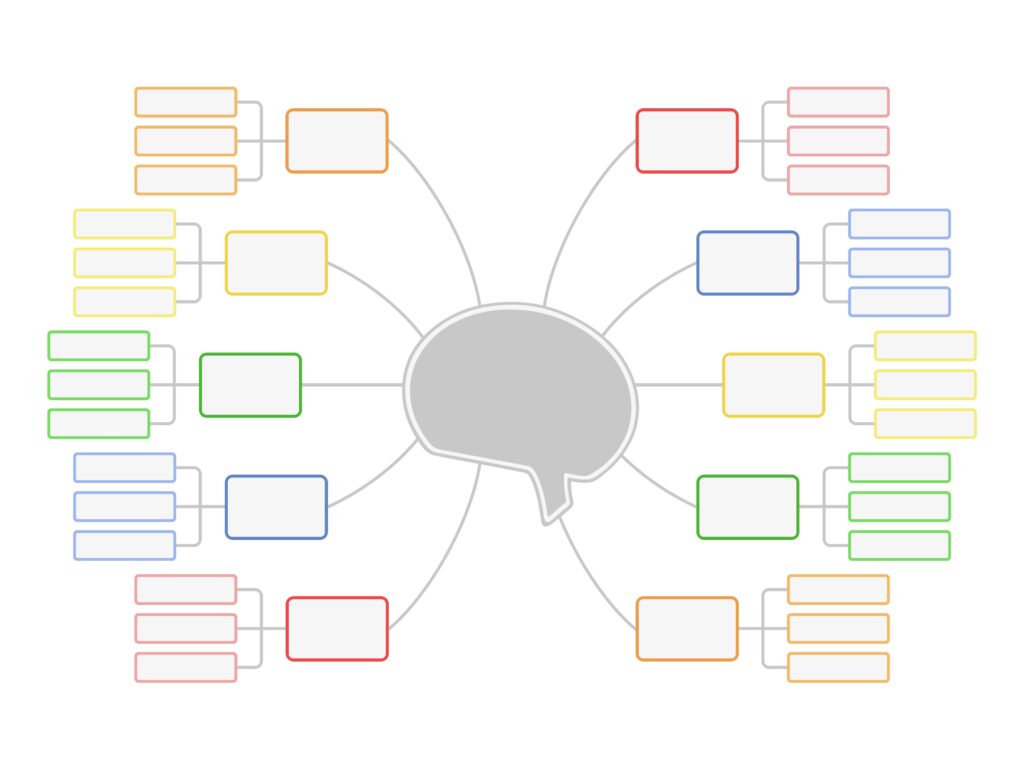
「木を見て森を見ず」
最近の記事でも記載していますが、「木を見て森を見ず」という視点から見てもより有効な問題解決の手法といえるはずです。
共通の利点
- バランスの取れた視点:
- マンダラチャートとロジックツリーの両方は、詳細な分析と全体的な視野を両立させることで、細部に埋没して全体を見失うことを防ぎます。これにより、「木を見て森を見ず」という状態を避け、バランスの取れた問題解決が可能となります。
- 視覚的な整理:
- どちらのツールも視覚的に情報を整理するため、複雑な問題や目標を直感的に理解しやすくします。これにより、細部と全体の両方を効果的に管理し、問題解決の効率を向上させることができます。
結論
マンダラチャートとロジックツリーは、細部に対する詳細な分析と全体像の把握を両立させることで、「木を見て森を見ず」という問題を防ぎます。これにより、バランスの取れた効果的な問題解決が可能となり、目標達成に向けた実行計画や解決策の策定を支援します。


