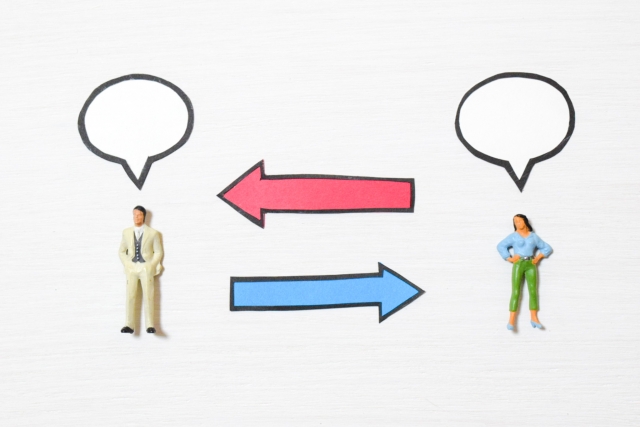責任分界点はどこにあるか
在庫管理についての役割は本社機能と支店機能によって異なります。
それぞれの役割や特徴についてまとめてみました。
本社の在庫管理
- 集中管理:
- 統一システム: 全支店の在庫データを一元管理するためのERP(Enterprise Resource Planning)システムを導入し、データを集中管理します。
- 統計分析: 過去の販売データやトレンド分析を用いて、在庫計画を立案します。
- 標準化:
- 発注プロセスの標準化: 発注手続きや在庫管理のプロセスを標準化し、効率化とミスの防止を図ります。
- マニュアルの作成: 各支店が従うべき在庫管理マニュアルを作成し、統一的な運用を徹底します。
- スケールメリットの活用:
- 大量発注によるコスト削減: 全支店分の在庫を一括で発注することで、仕入れコストを削減します。
- 在庫分散: 必要に応じて在庫を各支店に分散させ、バランスの取れた在庫配置を実現します。
- 供給チェーンの最適化:
- サプライチェーン管理: サプライチェーン全体の最適化を図り、在庫の流れを効率化します。
- 物流管理: 物流網の管理を強化し、在庫の移動コストや時間を最小限に抑えます。
支店の在庫管理
- 地域密着型管理:
- 顧客ニーズの反映: 支店はその地域の顧客ニーズを直接把握するため、在庫の種類や量を顧客の嗜好に合わせて調整します。
- 即応性: 地元の需要変動に迅速に対応できるため、急な注文や季節変動に柔軟に対応可能です。
- 独自の発注システム:
- 発注頻度: 支店はしばしば発注頻度を高くして在庫回転率を向上させ、無駄な在庫を減らすことを目指します。
- 発注量: 少量多頻度の発注を行うことで、在庫の保管コストを低減します。
- 在庫管理システムの利用:
- ローカルシステム: 支店独自の在庫管理ソフトウェアやエクセルを使用し、日々の在庫状況を管理します。
- リアルタイム更新: 在庫状況をリアルタイムで更新し、欠品や過剰在庫を防ぐためのデータを常に把握しています。
- 地域特性の反映:
- 季節商品やイベント対応: 地域特有のイベントや季節商品の需要を予測し、それに合わせた在庫を確保します。
議論を進めるために
前述の通り、支店と本社の在庫管理についての考え方は大きく異なります。
立場が違えば見えている景色が違い事は当然です。
座っている席が違えば言うことは違って当然です。
ではどのように議論が前に進むのか考えてみました。
支店は何に重点をおいているのか。大切にしているのか。
本社は何に重点をおいているのか。大切にしているのか。
それを理解し、それぞれの責任を果たすためにどのようなことをしなければいけないのか。
『目的』は同じ(はず)
『手段』は違う
結果から逆算して考えてみましょう。
本社は在庫を抱えず経営効率をあげることが『目的』
支店は在庫金額を抑えてP/Lの改善や在庫予算を達成することによって業績評価をあげることが『目的』
両者の『目的』は在庫金額を抑えること。在庫量を抑えること。
微妙に違うように見えて同じ『目的』
重点や視点、手段だけが異なることがわかります。
そこで大きな壁として立ちはだかるのが『立場』の違いです。
あらゆる場面でこのことが言えます。
細かく論じるつもりはありませんが、当たり前だと思いましょう。
ではどうするのか!
それを議論しましょう!!
ということです。
結論
ビジネスマンなら一度は耳にしたことがある言葉。
〇『内的要因・外的要因』『自己・他者』
〇『できること・できないこと』『したいこと・したくないこと』
という相反する状況。
これについてどこに位置しているのかを十分に理解することが大切。
自分にはなにができてできないのか。変えられて変えられないのか。
他者になにを求めて。なにを求めないのか。
当事者意識で客観的に図形化して判断することが大切です。
今回の議論は『在庫管理』についての話ではありましたが、
日々起こる事象について共通して言えることだと思います。
『結論』を見ることよって浮かび上がる『議論』の深み、成熟度。
薄っぺらい議論(議論とも呼びませんが、、、)をすることによる結論。
結論から浮かび上がる議論。
より大きな手で事象を把握し、より大きな森で草木を茂らせていかなければなりません。
その手が、その森がどのような大きさになるかは自分自身にかかっています。